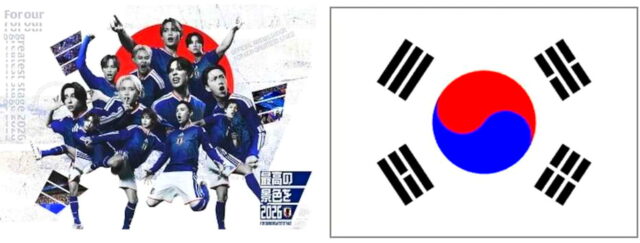2025年現在、全国で深刻化しているクマによる被害。連日報道されるニュースに心を痛めている方も多いのではないでしょうか。そんな中、2025年11月5日、アーティストの宇多田ヒカルさんが自身のX(旧ツイッター)を更新し、一部の週刊誌報道に対して強い苦言を呈したことが大きな話題となっています。
発端となったのは、宇多田ヒカルさんが過去にクマに関して発言した内容を、現在の被害状況と結びつけた記事でした。しかし、その記事の構成が、読者に大きな誤解を与える可能性のある「悪質な手法」だったと宇多田さん本人が指摘しています。
宇多田ヒカルさんが「クマが可哀想で泣いてる」「ハンターに天罰が下ればいい」などと発言した事実はあるのでしょうか?
この記事では、宇多田ヒカルさんが苦言を呈した週刊誌はどこなのか、問題となった記事の具体的な手法、そして「熊擁護派」と誤解されるきっかけとなった過去の発言内容について、詳しく掘り下げていきます。
宇多田ヒカルが自身の発言を利用した記事に苦言を呈した詳細
今回の騒動は、宇多田ヒカルさん本人のポスト(ツイート)によって明らかになりました。
2025年11月5日のX(旧ツイッター)投稿の詳細
2025年11月5日、宇多田ヒカルさんは自身の公式Xアカウントで、現在のクマ報道に関連して、自身の過去の発言が引用された記事がYahoo!ニュースなどで紹介されていることに触れました。
その記事を読んだ人から、「クマが可哀想で泣いてる」「ひどい!ハンターに天罰が下ればいい」といった過激な発言を宇多田さんがしている、と誤解した批判的な意見が届いていることを明かしました。
宇多田さん自身も「十年以上前とはいえ、んなこと言うわけないよね」と疑問に思い、記事を確認したといいます。
「本人の私でも騙されそうになった」その理由とは
宇多田さんが記事を確認した結果、驚くべき構成上のトリックが判明しました。
宇多田さんによれば、その記事は「SNS上のランダムな人たちの過激な発言を、そうとは明記せずに私の写真の下に掲載、そのまま私の話やほんとの引用が始まる、という構成」だったとのことです。
つまり、記事の冒頭や宇多田さんの写真のすぐ近くに、匿名のネットユーザーによる「クマが可哀想」「ハンターに天罰を」といった過激な意見を配置。その後に宇多田さんの実際の(しかし、文脈が異なる)発言やエピソードを続けることで、あたかもそれらの過激な発言を宇多田さん自身がしたかのように読者を誤認させる作りになっていたのです。
宇多田さんはこの手法に対し、「そんな手があるんかい」「本人の私でも騙されそうになったわ」と強い驚きと不快感を示し、「こういう世間の憤りを関係無い有名人に向けようとするのやめてほしい」と厳しく苦言を呈しました。
宇多田ヒカルが苦言を呈した週刊誌と該当記事の特定
宇多田ヒカルさんが「騙されそうになった」とまで言及した、問題の記事は一体どこのメディアのものだったのでしょうか。
該当記事は「週刊女性PRIME」と特定
宇多田さんがポストした日付(11月5日)や記事の内容、そしてネット上の反応などから、該当する記事は「週刊女性PRIME」が配信したものである可能性が極めて高いと見られています。
「週刊女性PRIME」は、大手出版社「主婦と生活社」が運営するニュースサイトです。
記事が公開された日付とタイトル
問題の記事は、宇多田さんが苦言を呈する前日、2025年11月4日に「週刊女性PRIME」で配信されたとされています。
記事のタイトルは、「クマ駆除に相次ぐ『かわいそう』も…宇多田ヒカルが漏らしていた『人間にとって脅威の生き物』の葛藤」といった趣旨のものでした。
この記事がYahoo!ニュースなど外部のプラットフォームにも配信されたことで、多くの人の目に触れ、宇多田さんのもとへ誤解に基づく批判が届く事態となったようです。
記事で使われた悪質な手法の具体的な内容
宇多田ヒカルさん本人が指摘したように、この記事の手法は非常に巧妙であり、悪質と受け取られても仕方がないものでした。
匿名の過激なコメントを写真直下に配置する構成
最大の問題点は、記事の構成です。
記事は、まず匿名のネットユーザーによる「駆除するなんて熊がかわいそう酷すぎる」「クマを殺す奴、ハンターに天罰が下りますように」といった、感情的で過激なコメントを引用します。
そして、それらのコメントのすぐ近くに宇多田ヒカルさんの写真を配置。この視覚的な配置が、読者に強烈な印象操作を行います。
読者に「宇多田ヒカルの発言」と誤認させるカラクリ
記事を流し読みしたり、見出しと写真だけを見たりする読者は、写真の近くにある過激なコメントを宇多田さん本人の発言だと勘違いしてしまいます。
記事の本文を注意深く読み進めれば、それが匿名のコメントであり、宇多田さんの発言ではないことが(かろうじて)わかる構成にはなっています。しかし、宇多田さんが指摘した通り、「そうとは明記せずに」紛れ込ませる手法は、意図的に誤解を誘発していると批判されてもやむを得ないでしょう。
法的な責任は回避しつつ、読者の誤解を狙う。まさに「そんな手があるんかい」と言いたくなるような手法です。
なぜ今、宇多田ヒカルが利用されたのか?クマ被害報道との関連
では、なぜ今、宇多田ヒカルさんがターゲットにされたのでしょうか。
2025年は、クマによる人身被害が過去最悪のペースで発生しており、社会問題となっています。メディアは連日この問題を報じており、世間の関心も非常に高まっています。
一方で、宇多田ヒカルさんは2006年に『ぼくはくま』という童謡をリリースしており、「クマ好き」というイメージが一部で定着しています。さらに、後述するように、2010年にもクマ問題についてXで言及していました。
メディア側が、現在の深刻なクマ被害と、宇多田さんの「クマ好き」イメージ、そして過去の発言を強引に結びつけ、対立構造を煽るような記事を作成した、というのが実情ではないかと推測されます。
宇多田ヒカルが「熊擁護派」と誤解された過去のツイート内容
今回、記事で利用された宇多田ヒカルさんの「過去の発言」とは、どのような内容だったのでしょうか。彼女は本当に過激な「熊擁護派」だったのでしょうか。
2010年当時の宇多田ヒカルの苦悩
問題とされた発言は、主に2010年頃にX(旧ツイッター)に投稿されたものです。この年も、2025年ほどではありませんが、クマの出没が相次ぎ問題となっていました。
宇多田さんは当時、クマが人里に出没する問題について非常に心を痛め、どうすれば良いか苦悩している様子をポストしていました。
「難しい問題だよね。東京なんかに住んでるだけじゃ分かったようなことは言えません」と、都市部に住む自分が軽々しく意見を言えないことへの葛藤も綴っています。
「駆除以外の方法はないか」模索する発言
宇多田さんは、駆除(射殺)が安上がりで早いという理由で選ばれがちな現状を知り、「麻酔銃を使って捕獲して森へ返すには、お金がかかる」と指摘。
「クマを森へ返すための予算を管理してる機関があるなら寄付したいな」と、駆除以外の選択肢を模索し、勉強しようとする姿勢を見せていました。
また、「今出来る対策と長期的な取り組み、両方が大切なんだね」とも述べており、多角的に問題を捉えようとしていたことがわかります。
2010年と2025年のクマ被害状況の違い
ここで重要なのは、2010年当時の状況と、2025年現在の深刻な状況は全く異なるという点です。
2010年頃は、まだ「くまモン」に代表されるような「かわいいキャラクター」としてのクマのイメージが強い時代でした。ネット上の反応にもあるように、当時は「津波」という言葉が楽曲(サザンオールスターズの『TSUNAMI』)に使われていたように、クマの脅威に対する世間の認識も今とは大きく異なっていました。
しかし、2025年は死傷者が多数出ており、クマは「人間にとって脅威の生き物」という認識が急速に広まっています。15年も前の、状況も認識も全く異なる時代の発言を、現在の文脈で切り取って報道することは、極めて不公正と言えるでしょう。
決して「過激な擁護派」ではなかった宇多田ヒカルの姿勢
さらに注目すべきは、宇多田さんが2010年当時、自らの発言を省みるポストもしている点です。
彼女は「熊の駆除をしたくなくてもしなきゃいけない人たちにすごくひどいことを言ってしまった…ごめんなさい」と、ハンターや関係者の立場を慮り、謝罪しています。
これらの発言を総合すると、宇多田ヒカルさんは決して「ハンターに天罰を」などと叫ぶような過激な熊擁護派ではなく、むしろ問題の複雑さに苦悩し、バランスの取れた解決策を真摯に模索していたことがわかります。
宇多田ヒカルとクマのイメージを結びつけた楽曲『ぼくはくま』の詳細
宇多田ヒカルさんとクマを結びつけるイメージの一つに、楽曲『ぼくはくま』があります。
2006年リリースの童謡
『ぼくはくま』は、2006年11月にリリースされた楽曲です。NHK『みんなのうた』でも放送され、宇多田さんが手がけた初の童謡として話題になりました。
歌詞は「ぼくはくま くま くま くま」「けんかはやだよ」といった、ひらがな中心の愛らしい内容です。
野生動物問題とは異なる楽曲の背景
この楽曲は、あくまでも「くまのぬいぐるみ」をモチーフにした童謡です。宇多田さん自身が「クマ好き」であったことから生まれた作品であり、当時の深刻な野生動物問題や駆除の是非について意見を表明したものではありません。
この楽曲のイメージと、2010年の発言、そして2025年の深刻な被害報道を、週刊誌が意図的に結びつけたと見られます。
「熊擁護派」「熊駆除派」といったレッテル貼りが行われる危険性
今回の騒動は、メディアによる安易な「レッテル貼り」の危険性を浮き彫りにしました。
複雑な問題の単純化
クマ被害の問題は、「人命か、動物愛護か」という単純な二項対立で語れるものではありません。
被害に遭う地域住民の安全確保は最優先であるべき一方、なぜクマが人里に下りてくるのか(環境破壊、エサ不足など)という根本的な原因の解決も必要です。また、駆除を担うハンターの高齢化や精神的負担といった問題もあります。
これほど複雑な問題を、「擁護派」「駆除派」とレッテル貼りして対立を煽る報道は、建設的な議論を妨げるだけです。
メディアリテラシーの重要性
宇多田ヒカルさん自身も「ネットや週刊誌の情報鵜呑みにしてるのは情報に弱い少数派が目立ってるだけだと信じてるけど」とポストしています。
私たち読者一人ひとりが、センセーショナルな見出しや巧妙な記事構成に惑わされず、情報源はどこか、事実は何かを冷静に精査する「メディアリテラシー」を持つことが、これまで以上に求められています。
宇多田ヒカルが苦言を呈したことに対するネット上の主な反応
宇多田ヒカルさんの勇気ある苦言に対し、ネット上では多くの意見が寄せられています。
週刊誌の手法への批判的な意見
最も多く見られたのは、週刊女性PRIMEの手法に対する批判です。
- 「これは悪質。宇多田さんが怒るのも無理はない」
- 「本人が騙されそうになるって、相当な印象操作だ」
- 「法的な責任を回避しつつ、読者の誤解を狙う一番タチの悪いやり方」
- 「アクセス稼ぎのためなら何でもありなのか」
など、メディアの報道姿勢を問題視する声が殺到しました。
宇多田ヒカルへの同情の声
同時に、誤解によって批判的な意見をぶつけられた宇多田さんへ同情する声も多く上がっています。
- 「宇多田さん、とんだとばっちりで可哀想」
- 「はっきりとXで反論してくれて良かった」
- 「有名税で済まされるレベルを超えている」
過去の発言を掘り起こす風潮への疑問
また、15年も前の発言を、現在の全く異なる状況下で持ち出すメディアの体質や、ネットの風潮に疑問を呈する意見も見られました。
- 「10年以上前の発言を今さら掘り起こして叩くのはおかしい」
- 「2010年と今とでは、クマ被害の深刻さが全然違う」
- 「時代背景を無視した切り取りはアンフェアだ」
クマ被害の現実とメディア報道のあり方
一方で、クマ被害の深刻な現実を訴える声もありました。
- 「北海道在住だが、クマは本当に怖い。かわいいイメージだけで語ってほしくない」
- 「被害に遭っている地域の人の気持ちを考えてほしい」
これらの意見は、メディアがセンセーショナルな対立構造を煽るのではなく、被害の現実や、複雑な背景を丁寧に報道すべきであるという、報道のあり方そのものへの問いかけとなっています。
まとめ
今回、宇多田ヒカルさんがXで呈した苦言は、一部週刊誌による悪質な記事構成の実態を明らかにするものでした。匿名の過激な発言と本人の写真を並べることで誤認を誘う手法は、多くのネットユーザーからも批判を浴びています。
宇多田ヒカルさんの2010年当時の発言を検証すると、彼女は決して過激な「熊擁護派」ではなく、むしろ問題の複雑さに苦悩し、バランスの取れた解決策を模索していたことがわかります。
クマ被害という非常にデリケートで深刻な問題に対し、メディアは安易なレッテル貼りで対立を煽るのではなく、事実に基づいた公正な報道を徹底することが求められます。そして私たち読者も、巧妙な情報操作に騙されないリテラシーを持つ必要があります。